
|
参考−1−付録1の付録の3.2節を参照されたい。 試験では、試料を飽和状態にするために試料内の空気を真空ポンプで吸引し、その後、容器に注水する。そのため、容器は気密が保てるものでなくてはならない。また、試料の飽和度を求めるためには、見かけの密度を計測できること、即ち、試料の体積を調製できることが必要である。そのため、容器は下部と上部に分けられている。 3.4.3. 試験手順の詳細 試験手順は、参考−1−付録1の付録の3.3節にも示したが、さらに詳細に述べる。 (1)真密度の計測 飽和度を求めるためには、真密度を計測する必要がある。真密度の計測方法については、適当なスタンダードを参照されたい。 (2)試料の挿入、締め固め及び飽和試料の作成 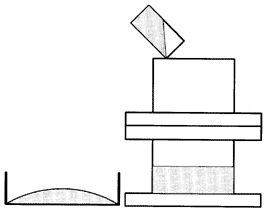
図3.4.3.1.試料の挿入(H8) 試料の挿入に先だって、容器内の空気を真空ポンプで吸引することにより、容器の気密を確認しておくことは、試験の失敗を防ぐため重要である。 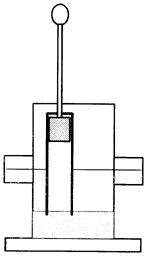
図3.4.3.2.締め固め(H8) 液状化物質判別試験においては、下部の容器の上面に沿って試料を切り取ることにより、試料の体積を調節する。下部の容器の容積は、約1,700 cm3であるため、試料はこれよりも充分に多く用意する必要がある。そのため、試験の際には、約2,400 cm3の試料を用意して、予め乾燥しておく。予め乾燥しておくのは、試料内の空気を吸引し易くするためである。 締め固めは6層にしたため、図3.4.3.1のように、一層当たり約400cm3の試料をビーカー等で測り、容器に入れる。 試料を容器に挿入したら、図3.4.3.2のように、各層毎に締め固めを行う。締め固めには、プロクターC法のランマーを用いる。 通常のプロクターC法では、200cm3当たり25回ランマーを落下させる。単位体積当たりの締め固めエネルギーを等しくするため、液状化物質判別試験の締め固めにおいてランマーを落下させる回数は、一層当たり50回とした。締め固めは6層で行うことから、一回の試験において、ランマーを300回落下させることとなる。 試料の挿入・締め固めを終えると、試料は下部容器から約3 cm程上まで達する。 試料を飽和状態にするためには、図3.4.3.3のように、試料
前ページ 目次へ 次ページ
|

|